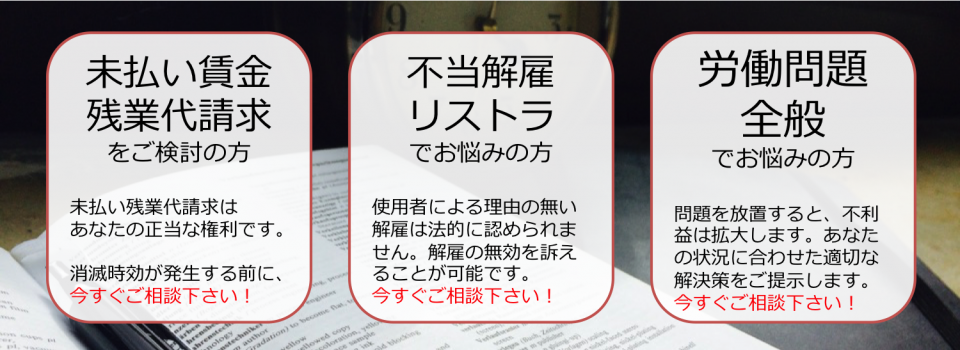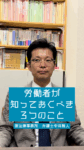法律相談等において、私が相談者や依頼者によくお伝えしていることを3つに絞って書いてみました。参考になさってください。弁護士中井雅人
1,すぐにサインをしない(署名・捺印は慎重に)
会社から「この書類にサインをして」と言われたとき、どのように対応していますか?じっくり内容を確認し、サインをしないという選択肢も視野にいれて考える人は少数派ではないでしょうか。
最終的にサイン(署名・捺印)をしなければいけない書類でも、絶対にその場でサイン(署名・捺印)をしなければいけない、ということはありません。
会社と労働者の間には、力関係があります。労働者の立場は弱く、安易にサインをしてしまうと、後により苦しい状況に追い込まれることがあります。
特に、退職の合意や、労働時間に関すること、競業避止など、サインひとつに状況が大きく左右されてしまいます。
最低でも1日、2日、時間をかけて、ほんとうにサインすべきなのか否かも含め、よく考え、できれば周囲にも相談し、サインするかどうかを決めるように心がけてください。
これは労働事件に限らず、紛争一般にあてはまることでもあるでしょう。
サインをするときには、じっくり考えましょう。
2,記録をする
残業代請求のためには、その時間に働いたという証拠が必要です。
労働時間を証明できるのは、タイムカードだけではありません。例えば、パソコンのログ、電子メール、LINE等のメッセージの送受信時刻、鍵の開閉記録、IC・IDカード、携帯等のGPS等、様々なものが証拠になり得ます。
パワハラ・セクハラを訴えるためには、ハラスメント行為の証拠が必要です。録音や録画は典型例ですが、LINEのやりとりも、証拠になり得ます。
このように、事件にもよりますが、例えばレシートが重要な証拠になることもあります。日報や日記もです。
柔軟な発想で、身を守るために証拠を残すということを、ぜひ心がけてください。
↓とても参考になる動画です↓
K・I・R・O・K・U・S・H・I・R・O(記録しろっっ・・・!)
3,はやめに相談(できるだけ労働弁護士への相談)
なにか気になることがあったとき、とにかくはやく相談すること。とても大切です。
もし弁護士等の専門家への相談のハードルが高いのであれば、相談相手は、まずは弁護士でなくても構いません。重要なことはひとりで悩まないことです。ご家族でもご友人でも、まず第三者に相談をすることで、一歩引いた客観的な視点で判断することができるかもしれません。
もちろん誤った情報には要注意です。
最近は、弁護士から見ても、優れたインターネット上の情報があります。
しかし、一方で誤った情報・不正確な情報も少なくありません。
また、当該インターネット上の情報自体は正確であったとしても、
その情報を正しく運用することは相当に難しいことです。
(自身に都合よく解釈してしまう、反対にネガティブに解釈してしまう、当該情報が問題となっている事案にあてはまらない等です。)
弁護士として相談者や依頼者と接していますと、もうすこしはやく相談に来てくれていたら、時効の関係で請求額がもっと増えたのにということや、もうすこし別のやり方があったのに、ということが少なくありません。
どんなに些細なことでも、まずは相談してみる、ということを大事にしていただきたいです。
YouTube動画も公開しました
労働者が知っておくべき3つのこと(YouTube動画も公開しました)。
① すぐにサインをしない(署名・捺印は慎重に)、② 記録をする、③ はやめに相談(できるだけ労働弁護士への相談)、自分の身を守るためにもぜひ心がけてください。